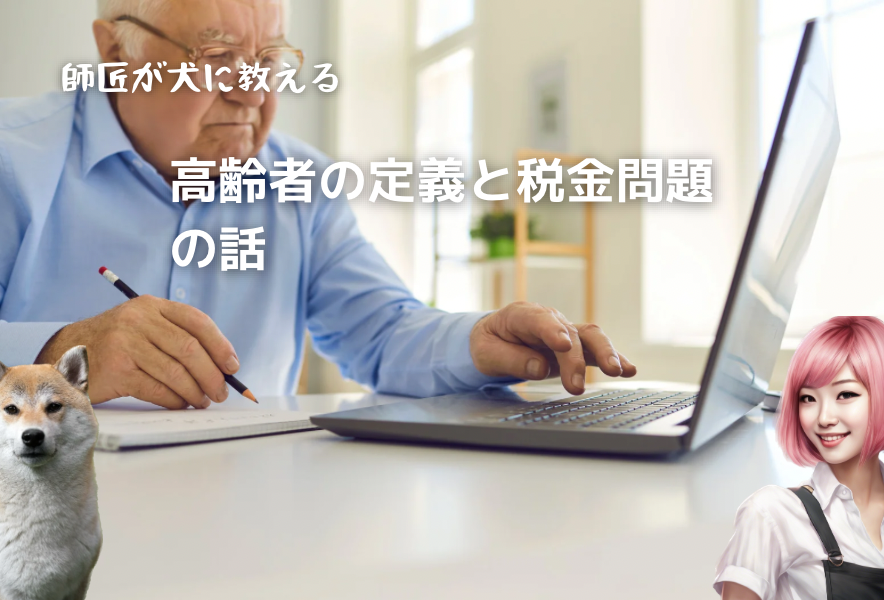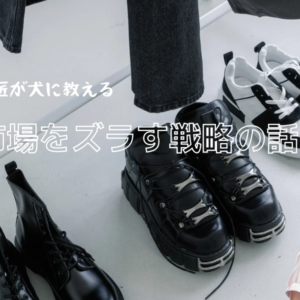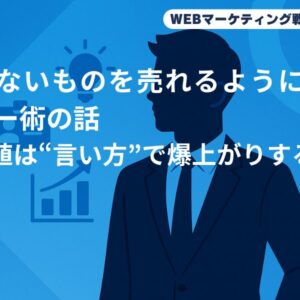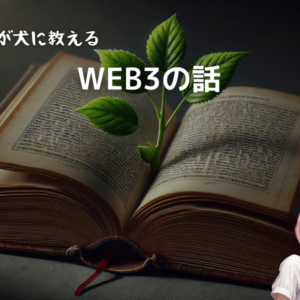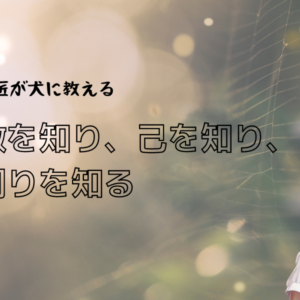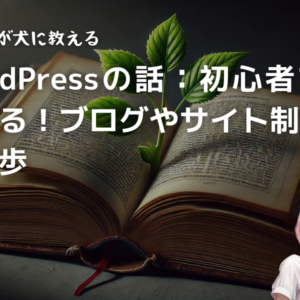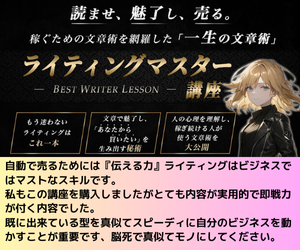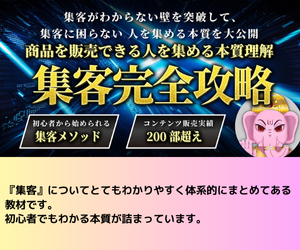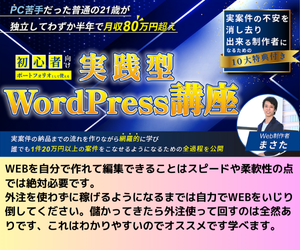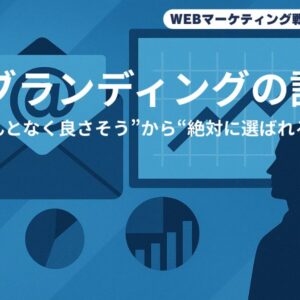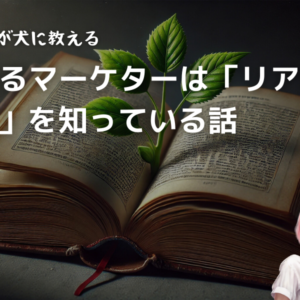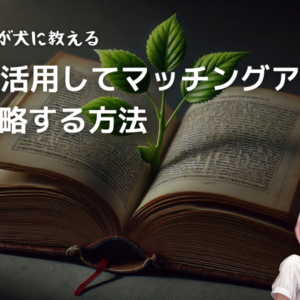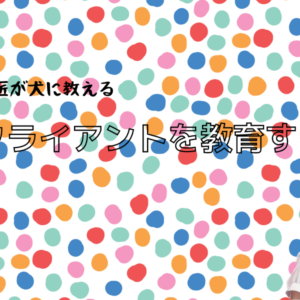ポチ: 師匠、ちょっと聞いてもいい?
日本の税金問題って高齢者が関係してることが多いんだよね?最近、健康寿命が伸びてるっていう話を聞いたんだけど、高齢者の定義を毎年見直すだけで、税金の問題って解決するのかな?
師匠: うん、ポチ、いい視点だね!確かに、日本の税金問題の大部分は高齢者に関連してるって言われてるわ。たとえば医療費や年金の問題ね。でも、「高齢者の定義を変えるだけで万事解決!」って言うのはちょっと楽観的かも。今日はその辺、詳しく話してみようか。
健康寿命が伸びる日本、高齢者の定義は変わるべき?
ポチ: そもそも、高齢者って何歳からのことを言うの?
師匠: 日本では、一般的に65歳以上の人を「高齢者」って呼ぶわよ。これは1960年代にWHO(世界保健機関)がそう定義したのが始まりね。でも、当時の平均寿命は今より短かったし、65歳でリタイアしてゆっくり暮らすってのが普通だったの。
ポチ: でも今はみんな元気で働けそうだよね!
師匠: そうなのよ。実際、厚生労働省のデータによると、2023年時点で日本人の健康寿命は男性が約73歳、女性が約76歳。だから、「65歳で引退するのは早すぎるんじゃない?」って意見も増えてるわ。
高齢者の定義を変えるメリット
ポチ: もし高齢者の定義を変えたら、どんなメリットがあるの?
師匠: 一番のメリットは、社会保障費の負担を減らせることね。たとえば年金をもらい始める年齢を70歳に引き上げたら、その分年金の支給総額が抑えられるでしょ?医療費の自己負担を少し増やすことで、若い世代の税金負担も軽くなるかもしれないわ。
ポチ: 若い人たちがちょっと楽になるってことか!でも、高齢者の人たちは困らないの?
師匠: 確かに、急に変えたら困る人も出るわね。だから、段階的に進める必要があるのよ。たとえば、今の50代以下の人たちは70歳から年金をもらう、とかね。でも、健康寿命が伸びてるおかげで、70歳でも働ける元気な人が増えてるから、働く環境を整えれば対応できると思うわ。
高齢者の定義を変えるだけで解決しない問題も
ポチ: じゃあ、高齢者の定義を変えれば、本当に「万事解決」になるの?
師匠: それがね、そう簡単にはいかないのよ。たとえば、少子高齢化の問題は「高齢者が増えすぎてる」だけじゃなくて、「若い人が減ってる」ことも原因でしょ?だから、高齢者だけに焦点を当てても、根本的な解決にはならないの。
ポチ: 確かに、若い人がもっと増えれば税金の負担も分散するよね。
師匠: そうね。子育て支援を充実させて出生率を上げるとか、移民を受け入れて人口を増やすとか、他の施策も必要になるわ。
まとめ:高齢者の定義を変えるのは一歩前進
ポチ: 師匠、今日の話をまとめるとどうなるの?
師匠: いい質問ね!じゃあ、要点を簡単に説明するわ。
- 日本の高齢者の定義は「65歳以上」だけど、これは昔の基準だから、今の健康寿命を考えると少し古い。
- 高齢者の定義を変えると、年金や医療費の負担が軽減される可能性がある。
- でも、それだけでは解決しない問題も多いから、少子化対策や労働環境の整備も重要よ。
ポチ: 高齢者の定義を変えるのは良いアイデアだけど、他の施策と組み合わせるのが大事ってことだね!
師匠: その通り!ポチも賢くなったわね!これからも一緒に日本の未来を考えていこう!